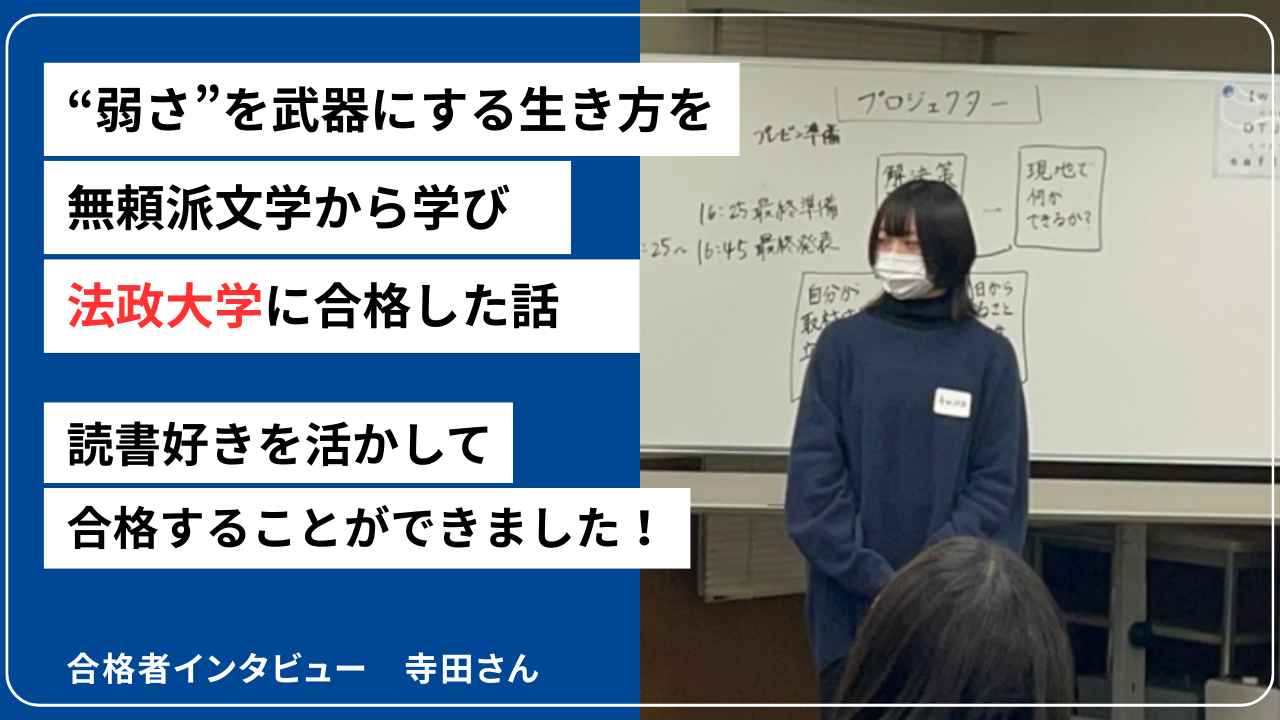無頼派文学に学ぶ自己尊重の在り方。病気と向き合う中で見つけた、「弱さを武器に」する人生
「弱さを受け入れること」が強さになる——法政大学文学部日本文学科に合格した寺田沙矢さんが、高校生活を通じて辿り着いた確信です。『人間失格』との出会い、坂口安吾の『堕落論』との衝撃、そしてカナダ留学での異文化理解。一見すると異なるこれらの経験が、やがて一つの志「編集者として、生きづらさを感じる人たちに無頼派文学を発信したい」へと収束していきました。しかし彼女の物語は、単なる「読書体験」ではありません。中学3年生の時、病気により一年間車椅子で生活した経験。その中で感じた「社会的な無理解」と「生きづらさ」。その体験が、無頼派文学の世界観と深く共鳴し、やがて彼女の人生の軸そのものになったのです。

(リザプロ課外活動の様子)
「悲観的な作風」に惹かれた理由
幼い頃から読書が好きだった寺田さん。怪奇文学や探偵小説など、幅広く読んできました。しかし、人生を大きく変える本との出会いは、高校時代に訪れます。
初めて『人間失格』を読んだ時、彼女は衝撃を受けました。
「普通の物語とは違う。主人公を否定するような書き方。読む中で、主人公と自分自身が重なる場面が何度もあった」
その違和感は、やがて深い興味へと変わります。太宰治を調べ、無頼派という文学潮流を知り、坂口安吾の『堕落論』を手にしました。
「『堕落とは人の本質であり、正しく堕落することで救いの道が開かれる』——この考え方に強く衝撃を受けた」
一般的に「堕落」は悪いものとされています。しかし安吾は、それを「救いの道」として捉えていたのです。
その時、寺田さんは気づきました。自分が人と異なる視点で物事を見ることが多く、それを「欠点」だと思っていた。周りから孤立することを恐れ、自分の意見や考えを言わず、周りに合わせることが多かった。しかし、安吾の考えを「欠点があってもそれを認め、どのように活かすかが大切だ」と解釈した時、何かが変わったのです。
「自分の考えや価値観を尊重し、はっきり自分の意見を言うようになった」
カナダ留学:「違い」が強さとされる世界
高校2年生の春、寺田さんはリザプロの講師陣に率いられカナダに短期留学しました。
カナダは移民国家です。様々な宗教、人種、文化背景を持つ人々が共存しています。そこで彼女が経験したのは、日本とは全く異なる価値観の世界でした。
「日本では、大勢いる考えや価値観が『普通』とされる。でも、カナダでは『人と違うこと』が強さとされている」
その違いに、寺田さんは心底驚きました。そして同時に、『堕落論』で読んだ思想が、ここに「生きている」ことに気づきました。
「多様な意見があることが社会を前に進める力になる」
カナダの社会に根付いた、その価値観が、彼女の心に響きました。
「生きづらさ」との直面——病気と社会的無理解
しかし、寺田さんの志を形作ったのは、何も読書やカナダ留学だけではありませんでした。
中学3年生の時、彼女は病気により、一年間車椅子での生活を余儀なくされました。それは、単なる「身体的な困難」ではなく、「社会的な無理解」との向き合いでした。
「エレベーターに乗った際、乗り合わせた方に車椅子に足をぶつけられたり、舌打ちをされたりした。バリアフリーの意味や目的を理解していたのに、自分が迷惑になっているのではないかと感じた」
その時、彼女が感じたのは、自分の「弱さ」や「違い」が、社会の中では「排斥される対象」になる現実でした。
そして、それが「生きづらさ」の正体なのだと気づきました。
無頼派文学が示す、「生きづらさ」への向き合い方
無頼派文学が描くのは、「人間の弱さ」と「社会への違和感」です。完璧ではない主人公たち。社会的期待に応えられない登場人物たち。
しかし、その作品の中には「救い」がありました。安吾の『堕落論』が示すのは、弱さを受け入れること自体が、人間の本質であり、そこからこそ「救いの道が開かれる」ということなのです。
つまり、無頼派文学とは「生きづらさ」と向き合わせてくれる文学なのです。
寺田さんが現代の日本社会に感じるのは、そうした「生きづらさ」が、まだ十分に言語化されていない、ということでした。
「現代の日本ではまだ『人と違うことは異様』という風潮がある。自己肯定感の低さ、失敗を恐れる完璧主義。そして、その先に待つのは——若者の自殺」
日本の若者の一番の死因は自殺です。いじめ、社会課題への生きづらさ、親の期待。多くの若者を、そこまで追い詰める現実があるのです。

(リザプロ課外活動の様子)
編集者として、「生きづらさ」と向き合う人々に光を届けたい
寺田さんが目指すのは、編集者としての道です。
「堕落論が当時の人々の生きる支えになったように、生きづらさを感じる人たちへ無頼派文学を発信したい。そして、現代の人たちが自己を尊重して生きていける社会にしたい」
それは、決して「完璧な人間を育てる」ことではなく、「自分の弱さを認められる人間」を増やすこと。「違いを受け入れられる社会」を作ることなのです。
SNSの普及により、比較が増えました。自分より優れた人を簡単に見ることで、自分の価値を下げてしまう若者が増えています。減点方式の教育や、「失敗=終わり」という社会の空気が、若者たちを追い詰めているのです。
その状況に対抗するために必要なのが、「人間の弱さを肯定する思想」——つまり、無頼派文学が示す「生き方への示唆」なのです。
法政大学での学び——理論と実践を統合する
法政大学文学部日本文学科での学びを、寺田さんはこう描きました。
二年次から文学コースで田中教授の下で戦後文学を学ぶ中で、無頼派文学を中心に研究する。特に、彼らが戦後という混乱期に「人間の弱さや堕落を肯定的に描いた背景」を、社会史や思想と照らし合わせて分析し、作品が「時代の価値観や生きづらさにどのように応答していたか」を探求したいのです。
そして、法政大学ならではの「野外調査」を活かして、無頼派の文豪の生家や作品ゆかりの地を訪れる。現場から「時代性」を体感し、単なる文献研究ではなく、「作品に息づく時代背景」を深く理解したいと考えています。
現地調査で得た知見を元に、作品が与える「生き方への示唆」を現代社会に重ねて考察する。「現代の生きづらさの問題」と接続させた上で、編集者として「時代の課題に応答する作品」を発信するための視野を広げたいのです。
「社会を否定するのではなく、人の弱さや多様な価値観を受け止められる人間に」
寺田さんが最終的に目指す姿勢は、シンプルで、そして深いものです。
「社会を否定するのではなく、人の弱さや多様な価値観を受け止められるようになりたい。そのうえで、他者の痛みや生きづらさを言葉で照らすことのできる編集者を志す」
現代の日本人は、自分を守るために偽り、我慢をして生きている人が多いと彼女は感じています。しかし、それは本当の意味で「自分を大切にしている」とは言えないのではないか。
多くの人が抱える課題に合う作品を発信し、現代に生きる人が「自身を尊重することができる社会」に貢献したい。
その想いが、無頼派文学に学ぶ自己尊重の在り方を、彼女自身の人生の軸としたのです。